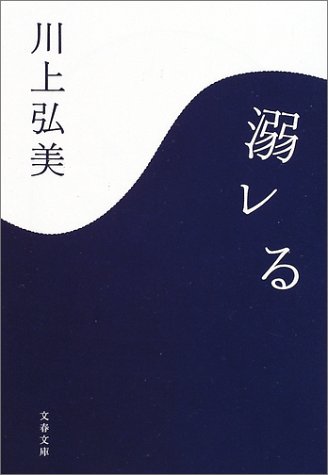タナダユキ「ロマンスドール」雑感

タナダユキ「ロマンスドール」角川文庫 2019年(単行本2009年発行) タナダユキ自身の脚本・監督による映画版をNetflixで2000年の夏に鑑賞。映画は、アートを志向していまいちうまく行かなかった作品という印象を持ったが、この原作に対しても同じような印象を持った。純文学を志向しているが、割合としてはラノベレベルの文章が多く、結果として中途半端な作品になってしまっているような。 主人公は園子のどこに魅かれて結婚を決意したのだろう? ルックスは語られている。ルックスだけなのか? そもそも出会ってから結婚に至るまで、主人公と園子は血の通った会話を殆どしてない。 園子が主人公のどこに魅かれたのかもよく判らない。 別にルックスと肉体だけに魅かれて結婚した、という話でも良いのだが、それなりに周囲の人間も登場して、相対化させようとしているものの、根本の話が曖昧なので、全体的にぼやけてしまっている印象。 映画版を見た時にも感じたが、セックスレスとか浮気とかの話も不要で、妻とラブドールに対する狂気の愛が等価に偏在して(主人公にとってその2つが全て、その2つが満たされれば他に何も要らない)、妻の死後に妻に似せたラブドールを完成させて彼岸に行って戻ってこれなくなる所に着地する方が、ありがちと言えばありがちだが、妻とラブドールを同じ女優が演じる映画の嘘でそれなりに狂気の愛の新しい形は描けたのではないか。 とにかくこの作品を映像で表現するなら女優のヌード必須。 その意味でも映画版は中途半端な作品だった。